「これだけは言いたいのは… 私ら(経営陣)が悪いんであって、社員は悪くありませんから! どうか社員のみなさんに応援をしてやってください、お願いします!
私らが悪いんです。社員は悪くございません‼ 善良で、能力のある、本当に私と一緒になってやろうとして誓った社員の皆に申し訳なく思っています!
ですから… 一人でも二人でも、皆さんが力を貸していただいて、再就職できるように、この場を借りまして、私からもお願い致します!」 (Wikipediaより引用)
1997年11月24日、テレビの向こう側で、大企業の社長が号泣しながら頭を下げる姿に、日本中が息を呑みました。四大証券の一角、名門・山一証券の自主廃業会見。そこで見せた最後の社長、野澤正平氏の魂の叫びです。
この出来事から四半世紀が過ぎた今なお、人々は彼のことを「かわいそうな社長だった」と記憶しています。しかし、その一言だけで彼の物語を片付けてしまうのは、あまりにも惜しい。
なぜなら、そこには単なる悲劇を超えた、一人のリーダーが絶望の淵で見せた究極の責任感と人間愛のドラマがあったからです。
この記事では、栄華を誇った山一証券がなぜ破綻したのか、そして「最後の社長」というあまりにも過酷な運命を背負った野澤氏が、なぜこれほどまでに人々の心を打ち、今もなお尊敬を集めるのか、その真実に深く迫ります。
栄華を誇った名門・山一証券はなぜ破綻したのか?
「かわいそう」な社長の物語を理解するには、まず、彼が背負うことになった「巨大な負債」がどのようにして生まれたのかを知る必要があります。
バブル経済の狂乱と「財テク」ブーム
1980年代後半、日本は空前の好景気、バブル経済に沸いていました。土地や株の価格は異常なほど高騰し、企業は本業で稼ぐ以上に、株や不動産への投資(財テク)で莫大な利益を上げる時代でした。
証券会社は、この財テクブームの主役です。「株は必ず儲かる」という神話のもと、大口の法人顧客に対し、積極的に特定の金融商品を販売していました。
禁断の果実「損失補填」と「にぎり」
問題は、その売り方にありました。山一証券を含む一部の証券会社は、大口顧客を逃さないために「損失は会社が補填しますから」という裏約束(損失補填)や、「必ずこれだけの利回りを保証します」という約束(にぎり)を半ば公然と行っていたのです。これらはもちろん違法行為でした。
バブル期は株価が上がり続けたため、この約束が問題になることはありませんでした。しかし、1990年代に入りバブルが崩壊すると、状況は一変します。
巨額損失を隠した「飛ばし」という禁断の魔法
株価の暴落で、顧客の資産には莫大な損失が発生しました。約束通り、山一証券は顧客の損失を肩代わり(補填)せざるを得なくなります。しかし、その損失を自社の決算で公表すれば、経営が一気に傾いてしまいます。
そこで使われたのが「飛ばし」という不正な会計処理でした。
これは、損失を抱えた金融商品を、決算期末が来る直前に、ペーパーカンパニーなど他の企業に一時的に買い取ってもらう手口です。これにより、決算書の上では損失が消えたように見せかけることができます。そして決算期が終わると、少し高い値段で買い戻す。この繰り返しで、損失の表面化を先送りし続けたのです。
2600億円の「簿外債務」という時限爆弾
しかし、「飛ばし」は問題を先送りするだけで、損失そのものが消えるわけではありません。むしろ、買い戻しの際の金利などで損失は雪だるま式に膨れ上がっていきました。
やがて「飛ばし」先を見つけることも困難になり、山一証券は自社の海外子会社などに損失を付け替えるようになります。こうして生まれたのが、会社の公式な帳簿(バランスシート)には載らない「簿外債務」でした。
その額、実に約2,600億円。いつ爆発してもおかしくない巨大な時限爆弾を、一部の経営陣は長年にわたって隠し続けていたのです。
伝説の号泣会見 – 魂の叫びが日本を揺るがした夜
この巨大な爆弾の存在を知らされずに社長の座に就いたのが、野澤正平氏でした。そして、運命の1997年11月24日を迎えます。
冷静な会見が一変した瞬間
会見の冒頭、野澤氏は用意された原稿を淡々と読み上げ、自主廃業に至った経緯を説明していました。しかし、会場にいた記者たちから厳しい質問が飛び交い始めます。
ある記者から、「社員はどうするのか(社員にどう説明するのか)」という質問がありました。
この一言が、野澤氏の中にあった最後の堤防を決壊させる引き金になったようです。彼は突然立ち上がり、声を震わせ、涙を流しながら、あの歴史的な言葉を叫んだのです。
「社員は悪くありません!」涙に込められた3つの想い
彼の涙は、単なる感情の爆発ではありませんでした。そこには、リーダーとしての痛切な想いが込められていました。
社員への「深い愛情」
会社の不正など何も知らず、日々真面目に働き、顧客のために汗を流してきた7,500人の社員たち。彼らには何の罪もない。その彼らが、明日から路頭に迷ってしまうことへの、どうしようもない申し訳なさと痛み。理不尽への「静かな怒り」
過去の経営陣が作り上げた負の遺産。その全ての責任を、なぜ今いる社員たちが負わなければならないのか。社員に責任を転嫁するかのような野次に対する、人間としての純粋な怒り。未来への「必死の懇願」
社長としてのプライドも、大企業のトップとしての体面もすべて捨て、ただひたすらに「どうか社員を助けてやってください」と訴える、父親のような必死の願い。
この会見は、謝罪会見であると同時に、一人のリーダーが自らのすべてを懸けて、仲間である社員の未来を守ろうとした「魂の決意表明」の場でした。日本中が、その姿に心を揺さぶられたのです。
「かわいそう」では済まされない。野澤社長が背負った過酷すぎる運命
野澤氏がなぜこれほどまでに同情と尊敬を集めるのか。それは、彼の置かれた状況があまりにも理不尽で、悲劇的だったからです。
就任わずか100日での破綻宣告
彼が社長に就任したのは、自主廃業のわずか3ヶ月前の1997年8月。不正会計問題で前任者が辞任した後の、まさに火中の栗を拾う形での就任でした。この時、彼はまだ2,600億円もの簿外債務の存在を知らされていませんでした。まさに、沈みゆく船と知らずに船長室の鍵を受け取ったのです。
「2,600億円の簿外債務」を知らされた日
社長就任後のある日、彼は役員の一人から別室に呼ばれ、極秘に打ち明けられます。
「実は、我が社には2,600億円の簿外債務があります」
その時の彼の衝撃は、察するに余りあります。それは、会社の死刑宣告に等しいものでした。
自らの責任ではない「過去の罪」
野澤氏自身は、営業(個人営業)畑出身のクリーンな人物で、不正には一切関与していませんでした。誰よりも真面目に山一証券を愛し、勤め上げてきた人物が、その会社の最も醜い部分の後始末を、たった一人で背負うことになったのです。この悲劇性が、人々の同情を誘いました。
最後の”しんがり” – 男・野澤正平の知られざる奮闘
本当の物語は、号泣会見の後に始まります。多くの経営者が責任を放棄する中、野澤氏は逃げませんでした。
7,600人の社員の「父親」として
彼は自主廃業後も社長室に残り続け、社員の再就職支援に全身全霊を捧げました。毎朝早くに出社し、山のように積まれた社員の履歴書一枚一枚に丁寧に目を通し、受け入れ先を探しては頭を下げて回る日々。それはまるで、我が子の将来を案じる父親の姿そのものでした。
社員たちを励まし続ける
会社が清算業務に入る中、不安でいっぱいの社員たちを、彼は励まし続けました。彼の存在は、崩壊する組織の中で、社員たちの唯一の心の支えでした。
最後まで貫いた「けじめ」
会社が起こした不祥事の「けじめ」を、彼は自らの人生を懸けてつけようとしたのです。上記の一連の行動は、ジャーナリストの清武英利氏に感銘を与え、後にベストセラー『しんがり 山一證券 最後の12人』として描かれました。「しんがり」とは、退却する軍の最後尾で敵の追撃を防ぐ、最も困難で最も名誉ある役割。野澤氏こそ、まさにこの「しんがり」を体現したリーダーでした。
【まとめ】野澤正平が遺したもの – 「かわいそう」を超えた、真のリーダーの姿
野澤氏の物語の入り口は、確かに「かわいそう」という言葉かもしれません。しかし、その奥には、現代の私たちが学ぶべき、あまりにも尊い教訓が横たわっています。
彼の人生は、「本当の責任」とは何かを私たちに教えてくれます。それは、失敗を隠蔽することでも、部下に押し付けることでもありません。組織が最も困難な時にこそ逃げずに矢面に立ち、仲間の未来のために自らを犠牲にできる覚悟のことです。
野澤氏は悲劇の社長でした。しかしそれ以上に、彼は絶望の淵から社員を守り抜いた、最高に「立派なリーダー」でした。
あの涙は、決して敗北の涙ではありません。一人の人間が、組織と仲間への愛を貫き通した、誇り高き涙だったのです。その誠実な姿が、時代を超えて私たちの胸を打ち続ける理由が、ここにあります。

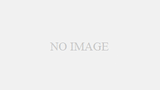
コメント