「学ぶ」という言葉の語源は「真似ぶ(まねぶ)」である、という説があることをご存知でしょうか。この言葉が示すように、古くから日本では、何かを習得する上での第一歩は、優れた手本を真似ることから始まると考えられてきました。一見、創造性とは対極にあるように思える「模倣」という行為が、実は学びの根幹をなし、やがては独自の境地を切り開くための不可欠なプロセスなのです。
学びの段階を示す「守破離」
この「模倣から独創へ」という学びのプロセスを端的に表した言葉が、武道や茶道、芸術などの世界で古くから伝わる「守破離(しゅはり)」という考え方です。これは、修行における3つの段階を示したものです。
守(しゅ): まずは師の教えや流派の型を忠実に「守り」、徹底的に真似る段階です。 基本となる知識や技術を、自己流を交えずに正確に身につけることに集中します。この基礎固めが、その後の成長の土台となります。
破(は): 次に、師から教わった型を「破り」、他の流派の教えや様々な考え方を取り入れ、自分なりに応用・発展させていく段階です。基礎が定着したからこそ、既存の型を客観的に見つめ、より良いものを模索することが可能になります。
離(り): 最後に、師の型からも、そして自身が作り出した型からも「離れ」、完全に独自の新しいものを生み出し、確立させる段階です。 ここに至って初めて、真のオリジナリティが生まれます。しかし、それは「守」と「破」という模倣と試行錯誤の積み重ねがあったからこそ到達できる境地なのです。
あらゆる分野に通じる学びの本質
この「守破離」の考え方は、伝統芸能の世界だけでなく、私たちの身近な学びにも当てはまります。例えば、子供が言葉を覚える過程を考えてみてください。最初は親や周りの大人の言葉をひたすら真似ることから始まります。 そして徐々に単語を組み合わせて自分なりの文章を作り始め、やがては自由に感情や考えを表現できるようになります。
スポーツの世界でも、一流選手はまず優れた選手のフォームを徹底的に模倣して基礎を築きます。ビジネスにおいても、成功した企業や起業家の戦略を学び、それを自社の状況に合わせて応用することで、成長の糸口を見つけることができます。
模倣は創造の土台
現代社会では、個性やオリジナリティが強く求められる風潮があります。そのため、「人の真似をすること」に対して、ネガティブなイメージを抱く人もいるかもしれません。しかし、白紙の状態から全く新しいものを生み出すことは、ごく一部の天才を除いては極めて困難です。
随筆家の白洲正子は「模倣も極まれば独創を生む」という言葉を残しています。まずは先人たちが築き上げてきた知識や技術を敬意をもって受け入れ、素直に真似てみる。その過程で本質を理解し、自分の中に深く根付かせる。そうして初めて、自分らしい表現や新たな価値の創造へと繋がっていくのです。
「学ぶことは真似ぶこと」。この古からの教えは、情報が溢れ、変化の速い現代においてこそ、私たちが立ち返るべき学びの原点を示唆しています。何か新しいことを始めようとするとき、あるいは伸び悩んでいるとき、まずは優れた手本を見つけ、謙虚に「真似る」ことから始めてみてはいかがでしょうか。その先には、きっと新しい自分との出会いが待っているはずです。
参考記事:大手前丸亀中学・高等学校

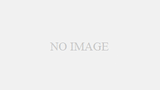
コメント