「あの人の話は分かりやすい」
「彼女の指示は的確で、迷わず動ける」
「彼の企画は、いつも本質を突いている」
あなたの周りに、そんな「頭のキレる人」「仕事ができる人」はいませんか? 彼らと自分との違いは何だろう、と考えたことはないでしょうか。才能や経験はもちろんありますが、実はその根底には、ある共通の「思考スキル」が隠されています。
それが、今回解説する「具体と抽象」の思考法です。
これは単なる言葉の知識ではありません。コミュニケーション、問題解決、アイデア創出、学習など、私たちが知的活動を行うあらゆる場面で絶大な効果を発揮する「最強の思考ツール」です。
この記事を最後まで読めば、あなたも「具体と抽象」という思考の武器を手に入れ、仕事や学習、日々のコミュニケーションの質を劇的に向上させることができるはずです。少し長くなりますが、あなたの思考をバージョンアップさせる旅に、ぜひお付き合いください。
第1章:そもそも「具体」と「抽象」って何?~リンゴの木で理解する基本のキ~
まず、基本から押さえましょう。「具体」と「抽象」と聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。一本のリンゴの木をイメージしてください。
「具体」とは? ― 手に取れる、目の前の一個のリンゴ
あなたが木の前に立って、枝に実っている「赤くて、ツヤツヤしていて、手のひらサイズの、このリンゴ」を指さしたとします。これが「具体」です。
形があり、ハッキリしている
五感で感じられる(見える、触れる、味わえる)
一つ一つの個別なもの
「うちで飼っている犬のポチ」「明日の朝9時の新宿駅での会議」「私が今飲んでいるこの一杯のコーヒー」など、誰が見ても同じものを指し示せる、個別の実例。それが「具体」の世界です。
「抽象」とは? ― すべてのリンゴをまとめる「果物」という概念
次に、そのリンゴも、青いリンゴも、隣の木のリンゴも、スーパーで売っているリンゴも、すべてをひっくるめて「これはリンゴだよね」と言ったとします。少し「具体」から離れましたね。
さらに、「そのリンゴも、バナナも、みかんも、全部まとめて果物だよね」と言ったとします。これが「抽象」です。
形がなく、頭の中で考える概念
多くの具体的なものから、共通点や本質を抜き出したもの
全体をまとめる、一般的な言葉
「果物」という言葉は便利ですが、それだけでは目の前のリンゴの味や形は分かりません。「愛」「平和」「戦略」「コミュニケーション」なども、様々な具体的な事象をまとめた抽象的な概念です。
重要ポイント:「抽象度の階段」で考える
「具体」と「抽象」は、「白か黒か」ではありません。なだらかな階段のようにつながっています。これを「抽象度の階段」と呼びます。
【上に行くほど抽象的(まとめる)、下に行くほど具体的(分解する)】
↑ 高い(抽象)
生き物
動物
哺乳類
犬
柴犬
うちで飼っている茶色の柴犬「ポチ」
今、私の足元でしっぽを振っているポチ
↓ 低い(具体)
この階段を意識することが、全ての基本です。「犬」という言葉は、「ポチ」と比べれば抽象的ですが、「動物」と比べれば具体的です。話が噛み合わないとき、多くの場合、相手と自分とで、この階段の違う段に立って話していることが原因なのです。
第2章:なぜ「具体と抽象の行き来」が最強のスキルなのか?
基本を理解したところで、いよいよ本題です。なぜ、この階段を自由自在に上り下りできることが、これほどまでに重要なのでしょうか。具体的なシーン別に見ていきましょう。
1.【コミュニケーション編】話が「伝わる人」と「伝わらない人」の決定的違い
仕事の悩みの多くは、コミュニケーションのズレから生じます。そのズレは、「抽象度のズレ」と言い換えることができます。
ダメな例①:抽象的すぎる上司
上司:「この資料、もっといい感じにしといて。よろしく!」
部下:「(”いい感じ”って何…? デザイン? 中身? 誰向けの資料なんだ…?)」
上司は「顧客満足度を高めるような提案書」という高い抽象度で考えているかもしれませんが、部下には伝わりません。結果、何度も手戻りが発生し、お互いに疲弊します。
ダメな例②:具体的すぎる部下
上司:「例のプロジェクト、進捗どう?」
部下:「はい。A社に電話したら担当者が不在で、B社にメールを送ったら自動返信が来て、C社の件は…」
上司が知りたいのは「順調か、問題があるか」という全体像(抽象)なのに、部下は個々の作業報告(具体)ばかり。これでは「木を見て森を見ず」で、上司は状況を判断できません。
理想的なコミュニケーションは「具体と抽象の往復運動」
上司:「来週の役員会議で使う資料なんだけど(抽象:目的)、競合A社との比較データを中心に(具体)、強みと弱みをA4一枚でまとめてほしい(具体)。何かクリエイティブな提案も一つ入れてくれると嬉しいな(抽象:期待)。」
部下:「プロジェクトの進捗ですが、要するに、オンスケジュールです(抽象:結論)。具体的には、A社とB社との契約は完了し(具体)、残るC社も来週には合意見込みです(具体)。したがって、来月末のリリースは問題ないかと(抽象:見通し)。」
このように、抽象(全体・目的)で話の枠組みを示し、具体(詳細・事実)で説明を補強し、再び抽象(結論・提案)でまとめる。このキャッチボールができるだけで、コミュニケーションの質は劇的に向上します。
2.【問題解決編】本質を見抜き、最適な打ち手を導き出す思考法
優れた問題解決は、まさに「具体⇔抽象」の往復運動そのものです。
Step 1:具体的な問題を見つける【具体】
目の前で起きている問題や事実を直視します。
「最近、部署内の若手社員の離職率が30%を超えている」
Step 2:抽象化して「本質的な原因」を探る【具体 → 抽象】
「なぜ?」を繰り返して、問題のレベルを上げていきます。
なぜ辞める? → アンケート結果を見ると「成長実感がない」という声が多い。【具体】
なぜ成長実感がない? → 「任される仕事が単調」「ロールモデルになる先輩がいない」。【具体】
要するに、何が問題なのか? → 「キャリアパスの不透明性」と「個人の裁量の欠如」が本質的な原因だ。【抽象】
ここで「単調な仕事がダメだから、面白い仕事をさせよう」という表面的な対策(具体)に飛びつくと、失敗します。抽象化して見つけた「本質的な原因」にアプローチすることが重要なのです。
Step 3:具体的な解決策に落とし込む【抽象 → 具体】
見つけた本質的な原因(抽象)に対して、具体的な打ち手を考えます。
「キャリアパスの不透明性」に対して → メンター制度の導入、1on1ミーティングの定例化、社内公募制度の拡充。【具体】
「裁量の欠如」に対して → 若手中心の新規プロジェクトチームの発足、一定金額までの決裁権の委譲。【具体】
このように、具体(問題)→抽象(本質)→具体(解決策)という思考の往復運動が、的確な問題解決を可能にするのです。
3.【アイデア・企画編】ありふれた発想から突き抜ける方法
イノベーションは、全く関係ないと思われる物事の間に「共通点」を見出すことから生まれます。これも抽象化の力です。
例えば、「飲食店の新しいビジネスモデル」を考えてみましょう。
具体Aを見る: 音楽や動画配信サービス。「Spotify」や「Netflix」は「月額定額制で使い放題」だ。【具体】
抽象化する: このビジネスモデルの本質は何か? → 「定期的に利用するヘビーユーザーを囲い込み、安定した収益を確保するモデル」だ。【抽象】
別の世界に転用(具体化)する: この抽象的なモデルを「ラーメン屋」に適用できないか?【具体B】
新しいアイデアの誕生: → 「月額8,000円で、当店の一部のラーメンが毎日1杯無料になるサブスクリプション」という企画が生まれる。【新しい具体】
このように、一つの具体例から本質(抽象)を抜き出し、それを別の分野に当てはめて新しい具体を生み出す思考法(アナロジー思考)は、斬新なアイデアの宝庫です。
4.【学習・スキルアップ編】学びを血肉に変えるインプット術
ただ知識を暗記するだけでは、応用力は身につきません。学びを本当に自分のものにするには、「具体」と「抽象」の往復が不可欠です。
具体 → 抽象(法則化・一般化)
歴史の勉強で、フランス革命、ロシア革命、明治維新といった個別の出来事(具体)を学びます。その上で、「これらの革命に共通するパターンは何か?」と考えます。「旧体制の腐敗」「新しい思想の台頭」「経済的な困窮」といった共通項(抽象)を見つけ出すことで、「革命が起きるメカニズム」という一段高い視点を得られ、他の歴史や現代社会を見る目も養われます。抽象 → 具体(実践・理解)
プログラミングで「オブジェクト指向」という抽象的な概念を学びます。教科書を読んだだけではピンときません。しかし、実際に「車」や「犬」といった身近なものをクラスとして定義し、コードを書く(具体)ことで、「なるほど、こういうことか!」と腹落ちし、深く理解できます。
知識(具体)を法則(抽象)にまとめ、法則(抽象)を実践(具体)で試す。この繰り返しが、本当の意味での「学習」なのです。
第3章:今日からできる!「具体と抽象の往復思考力」を鍛えるトレーニング
では、どうすればこの強力な思考スキルを鍛えられるのでしょうか? 難しく考える必要はありません。日常のちょっとした意識で、あなたの「思考の筋肉」は確実に鍛えられます。
魔法の言葉を口癖にしよう
この2種類の言葉を、意識して使ってみてください。
① 具体の世界に降りる(深掘りする)魔法の言葉
話がフワフワしていたり、理解が浅いと感じたりしたときに使います。
「例えば?」
「具体的には、どういうこと?」
「それって、誰が・いつ・どこで・何を・どうするの?(5W1H)」
② 抽象の世界に上がる(要約・本質を探る)魔法の言葉
情報が多すぎて混乱したり、話の全体像を掴みたかったりするときに使います。
「要するに?」
「つまり、一言で言うと?」
「これらの共通点は何だろう?」
「そもそも、この話の目的は何だっけ?」
会議で誰かが抽象的な話(例:「もっと顧客志向でいこう」)を始めたら、心の中で「例えば、どんな行動が顧客志向なの?」と問いかけてみる。逆に、細かい話が続いたら「要するに、問題はコストなの?品質なの?」と本質を探る。この思考のクセが、あなたを一段高いレベルに引き上げてくれます。
日常でできる簡単トレーニング
ニュースを見て「要するに?」を考える
日々のニュース(具体)に触れたら、「この出来事の背景にある、より大きな社会のトレンド(抽象)は何だろう?」と考えてみましょう。(例:タピオカ店の閉店ニュース → 日本のブームのサイクルの速さ、という抽象)読書メモの取り方を変える
本を読んで感銘を受けた一文(具体)を書き写すだけでなく、その隣に「この本から得られた一番の教訓は何か?(抽象)」を自分の言葉で書き加えてみましょう。「逆の視点」で説明してみる練習
もしあなたが普段、つい細かく説明してしまうタイプなら、意識して「結論から言うと〇〇です」と抽象的に話す練習をしてみてください。逆に、いつも話が大枠になりがちな人は、「例えば、先日のA社のケースでは…」と具体的なエピソードを交える練習をしてみましょう。
おわりに:思考の解像度を上げて、世界の見え方を変えよう
「具体」と「抽象」。この二つは、物事を理解するための**思考の「レンズ」**のようなものです。
具体的な世界にだけいると、目の前のことしか見えず、全体像を見失う「近視」の状態になります。
一方、抽象的な世界にばかり漂っていると、現実感がなく、行動に移せない「遠視」の状態になってしまいます。
本当に「頭がいい」人とは、このレンズのピントを自在に操り、具体的にもシャープに見えるし、抽象的にも広く見渡せる人のことです。彼らは、状況に応じて思考の解像度を瞬時に切り替え、問題の本質を捉え、的確な行動を起こすことができるのです。
今日から、あなたの会話や思考の中に「例えば?」と「要するに?」を取り入れてみてください。
その小さな一歩が、あなたの思考の階段を上り下りするトレーニングの始まりです。
この思考法を身につけたとき、あなたはきっと、これまでとは違う景色を見ているはずです。仕事の成果が変わり、人との対話が深まり、そして何より、世界をより深く、面白く捉えられるようになっている自分に気づくでしょう。
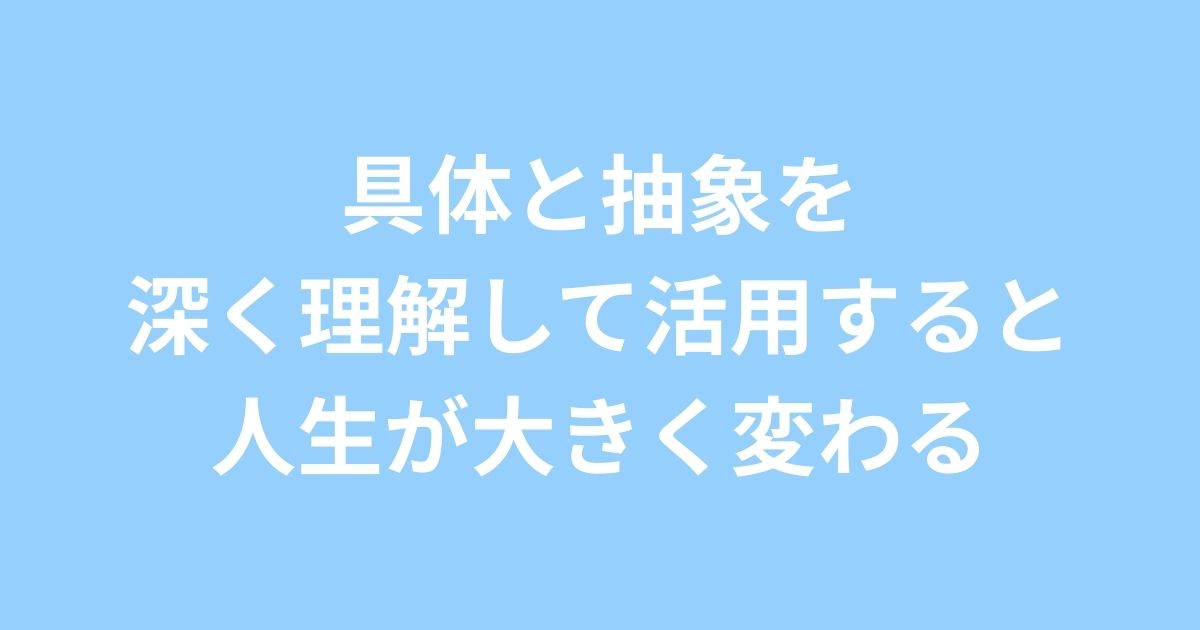

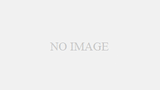
コメント